知的財産の管理会計
経営戦略のために
知的財産権制度の意義の変容 − 投資の保護へ
知的財産権制度の目的は、各法律の第1条に書いてある。例えば、特許法第1条には、「この法律は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。」とある。商標法第1条には、「この法律は、商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とする。」しかし、これは1959年にこの法律ができた当時の理念である。このような目的は、額面通りいまに当てはまるのであろうか。この当時、大卒銀行員の初任給は1万3千円程度であり、真空管で動く信頼性の低い17インチのカラーテレビが42万円した。大衆車(日産のブルーバード)が62万円で、マイカー時代の幕開けといわれた。日本の製造業がその存在感を国際的にも現しつつあるときであった。
しかし、そのような品質の良いものを作ることが付加価値の源泉であった社会は、経済成長の熱気とともに到来し、あっという間に過ぎていった。いま、知識が価値を生み出す社会となった。単によいものを作ることではなく、求められているもの、価値のあるものを生み出して、それを製造することが必要である。上で引用したそれぞれの第1条における「産業」の意味が全く変わってしまったといっていいだろう。そのような社会において知的財産権制度は何を保護するのであろうか。1959年に書かれた「目的」に答えがないことは明らかである。このシフトを図式化すると次のようなものになろう。
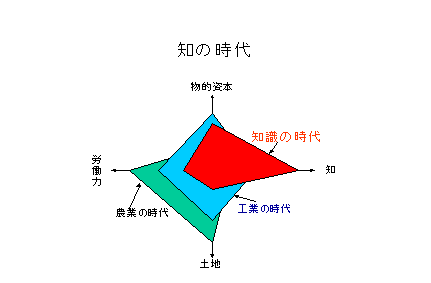
結論を先に言ってしまえば、知的財産権制度は、投資を保護する制度になってきた。特許権で見るとすこしわかりにくいかもしれないが、例えば、著作権制度で見ると明らかである。例えば、映画の著作権に特別の地位を与えて保護しているが、その理由は、決して著作権法1条の目的にある「文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする」からすんなりとはでてこないであろう。巨額の投資が映画の制作には必要なので特別な保護がいるということが本質である。そして、その与えられた保護のもとで初めて可能になる、プロジェクトの証券化といったファイナンス技術を利用して、映画が作られているのである。先頃「おニャン子クラブ事件」で再確認された「パブリシティ権」という判例上の財産権の源泉も著作権法の「目的」からはストレートには出てこない。データベースの保護にしても同じである。
商標の分野においても、欧米諸国においては、真正品であっても平行輸入(ヨーロッパでは域外からの並行輸入に限られる)は商標権の侵害となる。それは、国際的な市場というよりは、個々のローカルな市場がいくつもあるのが現実であって、その個々の市場において、マーケッティングや販売網の整備のための投資があり、それは商標制度によって保護するべきであるという認識が基礎になっている。
特許について単純化してみると、数十億円の研究開発投資をしたとして、特許出願を1件もしなければ、開発された技術を社会一般に無償提供したことと同じであり、投資のリターンを得ることができない。特許制度においても、投資の保護という側面はそこここに見えてきている。ここ数年のビジネス方法やバイオテクノロジー発明を巡るせめぎ合いもそのようなことから起こるのであろう。
バランスシートに載らないもの − 知的財産
一方、情報社会、知識社会の到来とか知価革命といわれている。おそらくそうだろうとは社会の動きと日々に仕事の中でも感じているが、ほんとにそうなのか。ここにおもしろい研究結果がある。米国のブルッキングインスティテュートの研究であるが、主要米国企業のバランスシートを、右に社債に代表される長期借り入れと自己資本として時価総額との和をおいて、左に機械設備や土地、建物などの有形資産を置き、左右をバランスさせるものが、特許、商標、ブランド、のれん価値、組織資源、人的資源などからなるといわれる無形資産となるものとしてみるものである。EVAなどの時価評価の考え方を取り入れて、たとえば有価証券等の含み益などを省略して細部を略して漫画化したものである。この「組織バランスシート」ほど、無形資産への企業価値のシフトを明確に示しているものはないであろう。
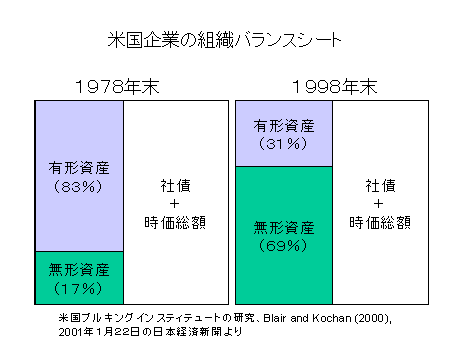
20年の間に、無形資産の占める割合は17%から69%にまで増大している。1998年末といえば米国のインターネットバブルが始まる前か、坂道を駆け上がり始めたころであるともいえるし、1978年は、ジミー・カーターが大統領で、アメリカは何ともいえない閉塞の雰囲気が漂っていた頃である。その20年の間に、企業の市場における評価は、有形資産を中心としたものから無形資産を中心に大きく変化していたのである。
ところが、このような無形財産は、いま企業が作るバランスシートには実際には載っていない。少なくとも出願や登録された権利として営業と分離して移転が確実に行える特許についても、簿価として取得価格である特許庁や特許事務所に支払った金額が記載されているのに過ぎないし、時価会計にしてもある一定の金額を個々の権利に割り当てるという考え方があるにすぎない。自己取得ののれん代(グッドウィル)やブランドの価値は、財務会計上全く評価されていない。
知的財産部門こそが経営の中枢へ
このように、知的財産制度の社会的意義が変化しつつあり、市場の企業に対する評価と付加価値構造が知識による付加価値に変化しつつあるいま、知的財産戦略が企業の命運を左右する。ここで、知財戦略といったが、より広くは、知識の管理と従業員の意識の改革に関する戦略といった方がいい。知識管理あるいはナレッジマネジメントというと技術の専門家としての特許部門の方々にとって違和感があるかもしれない。しかし、新しそうではあるが、ナレッジマネジメントとは、これまで特許部門が企業内で行ってきた活動に新しい服を着せただけのものである。畢竟、特許部は何十年も知識の管理を行ってきたのである。このことを、野中郁次郎教授の提唱するナレッジマネジメント理論を例にとって検証してみよう。
野中教授によれば、知の創造は「共同化」(Socialization)「表出化」(Externalization)「連結化」(Combination)「内面化」(Internalization)という四つのプロセスからなる。まず、「共同化」は暗黙知から暗黙知を創ることに始まる。経験を共有することによって、個人の暗黙知から暗黙知を獲得することである。「表出化」は暗黙知から形式知を創ることである。限られた範囲の人々の間でしか共有できない暗黙知を第三者にも分かるように言葉に変換していき、暗黙知を明確なコンセプトとして表現することである。第3のプロセスは「連結化」。「連結化」は「表出化」のプロセスによってグループレベルの集団が共有できるものとなった形式知を連結して、組織レベルの形式知に変換するプロセスのことである。そして、「内面化」が行われる。「内面化」は形式知を個人が真に身につけるために、表出化されて暗黙知から生まれた形式知を個人の暗黙知へと「内面化」するプロセスである。そして、野中教授によれば、知の創造プロセスには「場」が必要である。つまり内面化された意味を知識にするためには、共有された文脈としての「場」が必要である。個人と個人との関係、個人と環境との関係、つまり文脈としての「場」である。
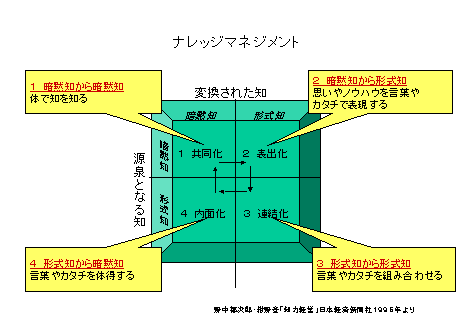
これを、野中教授の理論を、日々の活動へと結びつけて考えると、次のようなモデルが提案できる。もちろんいくつかの重要な要素を取り残した単純化ではあるが、実践のための一つモデルとしては有効であろう。
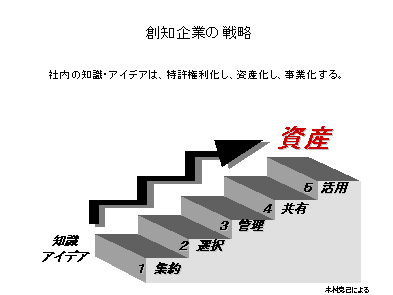
これは、いわゆる特許部が行ってきた活動と何ら異ならない。発明を奨励することにより暗黙知の共同化を推進し(発明者に働きかけ、特許情報を提供し)、暗黙知を掘り起こして表出化させ(発明提案書を書かせ)、形式知にして(特許出願にし)、それを連結化する(自社特許データペースなど種々の媒体を用いて表出化された知識を研究開発部門の共有化を進める)。内面化は、さらなる発明への刺激を提供することである。特許担当者は、特許という一つの文脈を提供することにより「場」を提供してきた。やってきたことが違わないとすれば、これからの知財部門は何を変えればいいのであろうか。答えは、やっていることの企業内の位置付けである。言い換えれば、これまで無意識に行われていたことを、体系的に考え直して、それを特許以外のあらゆる企業活動にも広めてゆく必要性である。考えてみれば、大部屋で、企業によっては墓地まで含めて人生を共有したかのような共同体の中で生まれてきた日本の生産技術の知恵を、ここで、より体系的に見直して企業内の仕組みとして広めてゆく必要が生じているのである。
しかし、単に知の創造の重要性を声高に叫んでも、厳しい競争と日々のビジネス活動の中でかき消されてしまいがちである。
会計帳簿がなければ経営できない
それでは、このような知の創造を企業経営に反映させるためには何が必要であろうか。
製造業においては軽視される傾向にあるかもしれないが、企業の継続的な活動は、会計帳簿と会計制度があってはじめて成り立つ。企業活動を一定の様式で記帳し、その記録された情報を説明可能にするアカウンティング(会計)の仕組みがあるからこそ会社を経営することができ、経営者という職種が成立する。この仕組みは、商法・証券取引法に定められているものである。もともとは活動結果を出資者に説明する方法として確立され、法に定められているものであるが、企業経営上の意思決定や戦略の策定をする上で必要な情報を使える形で汲み上げる仕組みとして機能している。そして、会計制度の仕組みがなければ現代の企業経営は不可能だと言いきってもいいだろう。
しかしながら、制度としてルール化されているいわゆる財務会計においては、企業活動のなかで重要な部分が抜けている。その不備を補い、企業経営や組織の管理に役立たせる方法として、商法や証券取引法に定められている以上の会計帳簿を作成して、経営状態を把握する管理会計制度を多くの企業が取り入れている。
「知的資産管理会計」という「管理」会計の意義
そのスッポリ抜けている部分の一つが「特許活動」であり、もう少し広くいえば「研究開発活動」である。これらの活動は、将来の収益をうみだすための投資活動であり、その成果物である特許は「知的財産権」、つまり資産的価値のあるものとして認識されていながら、財務会計上はそのようには表現されない。即ち、費用として毎期一括計上されるので、資産として計上されないのである。もちろん、研究開発費の管理や同戦略の立案などに管理会計的なアプローチはあるが、正当で客観性のある研究特許活動の評価に基づいた管理会計が実行されているとは思われない。
このことが、特許戦略や研究開発の策定、あるいは経営の意思決定に必要な、重要情報の汲み上げに、決定的な負の影響を与えている。企業経営が経営陣の直感に頼るものでいいわけがない。または、そう言うこと、つまり会計制度上に欠陥があることが、充分認識されていないのではないか。もし、「特許活動」や「研究開発活動」が会計上の欠陥を埋め合わすかたちで「ブッキング(記帳)」されれば、経営の意思決定が従来とは違った結果になるはずである。
企業の一層の効率化や収益化をはかるため、会計思想にもとづいた「知的財産会計」帳簿をつくることが求められている。この「知的財産会計」は技術開発活動とその成果を守る特許を管理会計に組み込むための記帳の仕組みをいい、これらの活動の意思決定、組織のコントロール、インセティブのあり方など、従来になかった手法や切り口を提供するものである。
技術開発や特許取得とその管理の問題点
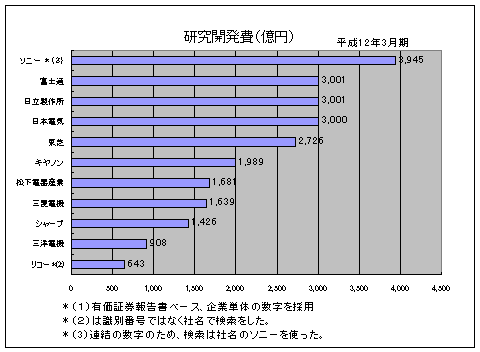
次のグラフは電気・精密機械業界で日本を代表する企業群の研究開発費である。その規模は数百億円から4000億円まで、巨大な数字を示している。当然ながらこの巨額の投資を効果的に使っていくために、各社その研究開発戦略を適切に立案することが重要である。グローバルな技術競争のなかで、企業の研究開発費の増大は今後も避けられそうもない。ますますその戦略性が求められるところとなるだろう。企業によっては、既に管理会計的手法による研究開発戦略の立案・管理を行っていると主張するかもしれない。差別化集中戦略、テクノロジー・ポートフォリオ・マネジメントを採用、あるいは、特許マップや自社データベースを利用、など研究開発や特許取得を戦略的に策定している会社もあるだろう。
しかし、再度考えてほしい。
(1)経営の意思決定に役立つ情報あるいは数値的なデータとして汲みあがる仕組みになっているか。
(2)開発プロジェクトなり特許開発が投資と投資収益の観点から客観的な情報として表現されているか。
(3)開発成果が事業化と収益に基づいた合理的な評価をする仕組みになっているか。
(4)その評価の仕組みに基づいた社内褒賞制度やインセンティブ制度になっているか。
(5)事業部制やカンパニー制など、企業組織に対応した戦略策定や評価制度になっているか。
これらのテーマについて、改善する必要があるとの認識があるならば、管理会計の考え方に基づき、その活動をブッキングしたものに基づいた経営情報が是非とも必要であろう。
視点を変えてもう少し考えてみよう。
(1)研究開発予算は経営陣からのトップダウンで、割り当て予算として決められる。その意思決定のための有用情報がシステムとして、あるいは経営判断の基礎になりうる形に整理されたデータとして経営陣に届くようになっているか。
(2)経営陣からみると、投資効果の算定ができない、いわばブラックボックス化した部門となっていないか。
(3)開発特許費は、販売促進費と同じで投資効果の測定は難しいと思っていないか。
(4)開発特許費の管理は、厳しい管理をすると研究者の優れた研究を阻害すると考えていないか。
(5)反対に、厳しい管理をしないと人やカネや時間の無駄が出てくると考えていないか。
(6)従って、ある程度の無駄は避けられないと考えていないか。
(7)開発や特許が完了した後の事後評価は難しいと思っていないか。
(8)そもそも、開発や特許は長期的な作業であり、期間を区切って成果を評価する会計システムの考え方になじまないと思っていないか。
(9)自社製品の開発のために行った研究と特許取得を、ライセンス料収入で評価するような問題の矮小化を行っていないか。
これらの問題点は、現在の管理方法のなかで、多くの企業が持っているテーマとも言える。
しかしながら、プロパテント・技術重視の経営を目指し、競争力を高め、効率を追求する経営が求められるなかで、これらの問題点は今後ますます経営上のテーマとして顕在化し、解決を求められる。
特に、企業における研究開発投資、特許開発費が巨大な金額だけに、その投資から得られる収益を正確に把握出来ないとすれば、また、その結果アカウンタビリティの欠如ということになれば、企業経営者は大きなリスク負っているといわざるを得ないであろう。今、知財戦略について外部や株主に自らの言葉で説明できる経営者がどれだけいるだろうか。
経営と特許・知財における乖離現象
企業の特許部或いは知的財産権本部などで行われているのは、多くの場合特許管理又は知財管理といわれている。企業によっては、独自のデータベースを構築し、かなりの投資を行っている。その中身は年金管理や包袋管理といった庶務的な管理から、自社保有特許のデータベース、独自の特許マップ構築など、戦略的な開発計画の策定に役立たせるための情報管理をする企業もある。これらは、研究開発計画、権利取得計画、権利強化など確かに企業経営上の重要な策定や決定に役立つ。
しかし、企業活動としてそれぞれの収支の決着をつけなくてよいのだろうか。実際には企業における特許管理は特許情報活動や特許取得活動が中心であると思われる。つまり、企業経営に本来必要な経営情報の汲み上げや経営判断をするための経営情報の提供がなされているとは思われない。特許や知財の世界ではその必要はないのか。プロパテントとは、特許・知財部門の問題であって、経営の問題ではないのだろうか。
当然企業のレベルにより、管理のためのインフラ整備、機能にはかなりの差がある。しかし共通して言える事は、企業経営に必要な情報が経営に汲みあがっていく機能が欠落している点である。企業経営は一定期間内に自らの活動の決着を客観的に評価し、報告できる機能がもとめられる。特許・知財の部門は例外なのであろうか。
特許・知財の分野にはそのアカウンティング(報告)機能が備わっていないので、実際にはする方法がない、というのが正確な表現だろう。これは産業界共通の問題であると思われるし、欧米でも同じかも知れない。
知財部門はコストセンターではない
企業の特許・知財活動費用は研究開発費及び研究設備費の一部と関連部署の人件費、出願費用の合計からなる。これらは財務会計上、一般管理費として費用計上されるので、当然ながら貸借対照表に資産計上されることはない。これが第一の問題点。また、一般的には予算計画で配分されるので、表現はよくないかもしれないが、交際費と同じ。配分されたものは消化される性質のものである。これが第二の問題点である。ここに、投資収益という考え方が希薄になる土壌がある。
多額の費用を投じた結果の評価は、研究の成果、出願の件数で計られることになる。目的の第一はそこにあるのだから、その評価は当然ではあるが、企業経営としてはそれでだけでよいはずがない。企業内の個々の活動が企業の目的である収益化にどのように寄与し、投じた金額にふさわしいものであったか。その評価が本当に出来ているのだろうか。無形財産の評価は、客観的な市場の欠如、評価対象の変動などに起因する本質的な困難性をはらんでいる。ここで言いたいのは、何も正確無比な評価が必要であると言うことではない。無形資産評価の特性として必然的に不正確さを内包したものであったとしても、知的財産の価値と企業内における位置付けをほぼ正しくとらえうるものであればよい。
「知的財産の価値を最大限に高めて、利益を生み出す仕組みを作り上げていくことが必要である。」というのが、プロパテントの精神である。そうだとすると、現在の特許・知財における機能・仕組みには更なる工夫が必要となる。知的創造サイクルの全ての循環において、効率化・収益化の結果が検証できる機能と仕組みをつくりだす必要がある。活動結果としての収益バランスを検証するツールを経営が持たないために、開発部門や特許・知財関連部門は、コストセンター的立場に放置されている。言葉を変えれば、特許・知財部は経営に情報をあげるツールを持たないがために、経営は自らの理念と戦略を打ち出す事が出来ず、社内に向かってのアカウンタビリティを発揮できない。従って知財関連組織での理念と戦略の共有化が出来ないという悪循環に陥っている。出願代理人などは、究極のコストセンターに位置付けられ、一定報酬内での件数消化に陥らせ、有用な外部頭脳を活かしきれないでいる。組織の内外における研究開発部門の機能・人材を活かしきれていないといったらいいすぎだろうか。
企業における特許・知財部門のあり方については、従来とは切り口の違うアプローチによる新しい仕組みを作り出す必要がある。
研究開発と知的財産のための知財管理帳簿を作れ
これまで見てきたように、研究開発を含めて見た特許部門に会計思想を導入するには、多くの障害というか、先入観が邪魔をしてきたように思われる。しかしながら、我々は、管理会計という財務会計から派生した管理ツールを既に持っている。管理会計にルールはない。財務会計は外に向かって企業活動を説明する役目であるから、法や制度による共通のルールに従わなければならない。一方、管理会計は企業内の管理ツールであるので、その企業の最も適した方法を採用(むしろ創るといった方が正しかろう)すればよいのである。その基礎となる記帳を「知的財産管理帳簿」と名づけよう。
その中心的な考え方は、
(1)開発特許部門はコストセンターではなく、投資部門であること。
投資は期待収益を担った資産として認識され、継続的な企業活動のなかで、資産の積上げの合計と減価償却の対象として認識されること。
(2)その資産は、研究開発と特許活動の成果として、その企業内の製品、ノウハウ、競争力のそれぞれの構成として個別計算されると同時に、それらから生み出される利益の源泉がいくらかを投下資本と考えられるべき予算との見合で評価されること。
(3)特許に関連した活動とその費用を、研究開発への投資と一体に考えること。
(4)これらの情報は管理会計の仕組みのなかで、経営の意思決定に有用な、加工され洗練された経営情報として、経営のトップに迅速に伝わること。
管理会計の仕組みから汲み上げられた活動評価は、各事業部・カンパニー単位、各事業責任単位、或いは部・社員単位に表現される評価制度を構成する。
知的財産会計は技術関連部門へ管理会計を導入するための基礎となるものである。その最終目的は、組織をいかに効率良く動かすかという、まさに経営のテーマへ直結するものなのであり、最終的にめざすところでもある。
特許開発や研究開発は長期的な戦略に基づき活動が実行されるものであるので、もともと会計的な考え方になじまないと考えている人がいるとしたら、大変な間違いである。長期的な活動であるからこそ、その活動(投資活動)を期間にまたがったトータルな数字として記録し、検証するツールが必要なのである。特許開発や研究開発の活動は、投資として認識され、その投資額は資産として毎期累積計上される。その累積された資産は、業務責任単位(あるいはもっと細分化された活動単位でもよいが)における彼らの業務に対し、その全資産を費用として課すことになる。そして費用として課した上で、各単位でどれだけの収益が得られたかが検証される。
「資産は費用なり」という言葉がある。累積された資産は、各業務単位あるいは活動単位で分けられているので、それぞれの決められた期間で費用として償却される。そこでは、各責任単位や活動単位、あるいは対応している製品単位ごとの、収益力や効率がデータとして把握することが可能となり、同時に各単位の目的に応じた期間での評価が可能となる。この評価方法は、開発計画の策定、その中間評価や事後評価を長期的な尺度で可能とする。その結果目先の企業収益のブレに影響されない、計画の策定や評価、あるいは意思決定を助ることになる。
もう一度繰り返しておく。研究開発と知財活動の費用は、投資である。
知財管理会計と研究特許活動の概念図
![]()
![]()
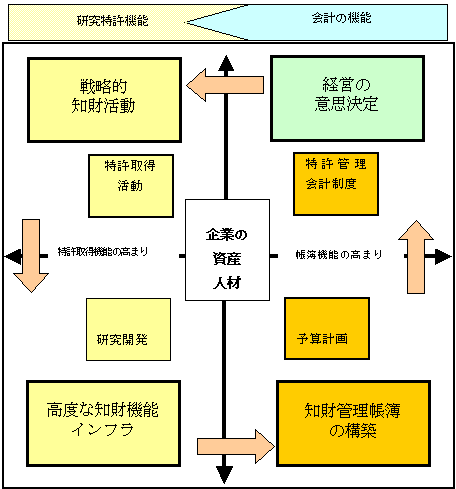
無形資産のオンバランス化の動き
上述のブルッキングインスティテュートの研究成果に見られるような認識は米国では一般的になりつつある。無形資産が含まれてない財務報告は「アンティーク」であるといわれ、証券取引委員会(SEC)の元コミッショナーらが新たな情報開示モデルを提言するなど、オンバランス化への動きは急である。オンバランス化とは、企業独自の管理会計ではなく、一般的な財務会計に無形資産の価値の計上を義務づけて、より完全な情報開示を企業に求めようとすることである。同時・多重利用が可能である、不確実性が大きい、市場が存在しないといった特性により、無形資産の評価は困難ではあるが、必要な客観的評価の試みも進んでいる。この試みは、無形資産の時価評価を求めるものである。一方、企業内の管理会計はその無形資産の取得原価を算定するツールでもある。
時価評価による企業価値計算は、取得原価の算定があってこそ企業経営上意味のあるものとなる。オンバランス化はまさにこの両面から求められることになろう。
改めて、知財戦略あるいは知識戦略へ
強い権利を取得し、コア事業の権利強化をすすめ、権利の穴を埋め、訴訟能力を高める。あるいは、休眠特許の有効利用や未使用特許のライセンス供与など、特許資産の収益化もプロパテントのテーマである。研究開発、特許開発の予算計画において、事前評価を充分にする。計画内容やプロジェクト単位での、需要予測、技術比較、開発スケジュールなどの面から評価をしていく。確かにその通りなのだが、何かが不足している。管理スタンスや意思決定での明快性とか合理性とか、良い表現が見つからないが、何かが欠けていると感じられる。
それは、技術開発関連部門の活動を社内情報として、充分に汲み上げる仕組みがないのではないか。何かが欠けていると感じさせた原因が、そこにあるのではないかと考えた。その欠けたものを補う支援ツールを持てば、企業におけるプロパテントの本当の仕組みができる。
「知的財産管理会計」という管理会計手法の導入でそれを解決できる。その導入には当然、軋轢、困難な問題、試行錯誤などの障害はあるだろう。
しかしながら、企業活動が競争力を維持し、継続しうるのは、自らの活動を客観化し、その客観化された情報を基にして、適正な経営判断を成し得て来たからなのではないのか。
このことに恐らく例外はないだろう。